|
||
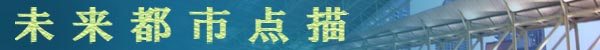 |
||
|
||
| ★未来都市点描/アイテム&システム編 | |
| G-maは、希望を感じさせる未来予想図のデザインに大きな関心がある。 創作世界観GDWも、そうした未来への関心がどこかで原動力になっているし、 (ただしGDW世界観自体は未来に限定せず現代や過去も扱う) 過去に1度はプロのデザイナーや建築士を志した人間でもある。 リアル空想プロジェクトももちろん、こうした思いからできたコンテンツだ。 未来都市点描は、G-maが現実世界で「これは未来的だ」と(主観的に)感じた、 建築物を始めとする様々なデザインについて、独自の評論を交えて紹介したものである。 ただし“未来的”と言っても、個々人がイメージする未来予想図には差があるため、 あくまでも「G-maが思い描く希望的未来図」であることをお断りしておく。 このうち、当ページではアイテム&システム関連の近未来ネタについて取り扱う。 建築物やメカニックを除くガジェットを扱っていると考えて差し支えなく、概ねデジタル・IT組だが、 評価基準としてはいちおう、それが全てではないつもりである。 また英数・50音順で並べており、多くなると途中から別ページに飛ぶので注意(笑) ICカード&スマホ決済 VR&AR(XR追記) 緊急地震速報 空調服(ハンディファンの解説を含む) デジタルサイネージ(デジタルペーパーの解説を含む) プロジェクターマッピング ペロブスカイト太陽電池(全固体電池の解説を含む) ホログラムボタン |
|
| |
|
| ◆ICカード&スマホ決済/気付けば目の前にあった近未来 | |
| 20世紀後半に、未来のライフスタイルとして提示されていたガジェットの1つが電子マネーである。 そう、今で言うICカードやスマホ決済につながる発想は当時すでに考案されていたのだ。 もっとも21世紀を迎える前に、クレジットカードやプリペイドカードは登場していたわけなので、 アイデアそれ自体は必ずしも目新しいものではないとも言えるだろう。 (コンピュータもデジタル機器のパイオニアだが、初登場は筆者が生まれる前の話である^^;) 2010年代が終わりを迎えつつある今“キャッシュレス・スタイル”が1つの社会現象と化している。 (このテキストは2019年の秋に書いたものです) 保守的な日本ではまだ現金取引という“伝統”に傾斜する傾向が強いものの、 国際社会ではこの数年、電子マネーによる取引が急激に増えており、 「現金取引を一切しない店舗(電子取引専用店舗)」が今や、普通に登場する時代を迎えているらしい。 こういうガジェットを使いこなす限り、「スマホさえあれば生活できる」時代になっているわけだ。 筆者はまだスマホ決済というガジェットに慣れられていないが、交通系ICカードはよく使う。 残額が減るたびにチャージする必要はあるものの、カード1枚で生活できるのは同じだ。 依存するほどにハマッてはいないものの、ICカードがないと不便に思う程度には使用頻度が高い。 上記の通り日本は保守的な上、デジタル技術への不信感が根強いというが、 政府広報もキャッシュレス業務改革を積極的に推進しようとしているようである。 業界大手のネット管理企業などが扱う“仮想通貨”も広義にはこのジャンルと言えるかも知れない。 恥ずかしながら筆者、まだこのガジェットがどういうものか良く知らないのだが、 現実世界の通貨に代わるものというよりは、金融証券のような扱いをされているように見える。 (仮想通貨の“信奉者”は既にいるようだが、まだ現実の通貨に取って代わるまでではないようだ) ネット内の会員ポイントの延長のようなものと考えれば良いのだろうか?(適当) キャッシュレス時代という世相を“礼賛”し、現金取引という“伝統”を批判する声もあるが、 「デジタルが全てに取って代わる」かのようなデジタル万能論は少々危うさを内包する。 単なるアナログオヤジのボヤキではない……選択肢のない“依存”や“独占”は危険だからだ。 人間という生き物それ自体は、どう頑張ってもデジタルにはなれない(脳を丸ごとチップ化しない限りは) デジタルの利点は否定しないが、それさえあれば何も要らないという考えには賛成できない。 多様な選択肢があるからこそ、未来が豊かになると筆者は信じる人間である。 |
|
| |
|
| ◆VR&AR/現実世界に割り込む空想世界(2021/10追記) | |
| 20世紀後半に、未来のライフスタイルとして提示されていたガジェットの1つがVRである。 仮想現実と訳されることが多く、HMD(ヘッドマウントディスプレイ)などを使い、 視界にCGなどの電子映像を投影する技術体系のことを指す。 当初は単に「架空の映像を疑似体験する」程度のものであったが、 今ではそれを「擬似的に触る」技術の開発が進んでいると言われている。 現実にはない電脳空間の物体を、現実の物体のように触り、扱えるようになるらしいのだ。 HMD方式ではないが、「映像に合わせて座席が揺れるアトラクション」もVRの1つだろう。 当初は大規模なテーマパーク向けの大掛かりなものであったが、 (それでもジェットコースターなどに比べればコンパクトなスケールの施設と言える) 1990年代から2000年代にかけて、自動車のキャビンほどのサイズを持つ“量産機”が登場し、 ショッピングモールのアミューズメント施設などに導入されてもいる。 こちらも新しい機種はドライアイスや水しぶきの噴射で臨場感を引き上げている。 更に2010年代に入って、にわかに注目を浴びるようになったのがAR(拡張現実)である。 こちらは完全に電脳空間に人の5感が入り込むVRではなく、 「現実世界の風景に電子情報を体感的に投影させる」技術体系のことを意味する。 例えば「スマホを覗く」という作業制約はあるものの、CGキャラがリアルの風景の中に登場する、 大人気ゲーム『ポケモンGO』もこのAR技術を使ったものであることは有名だろう。 「人気ポケモンが出る」という情報で、スマホを持った青少年の集団が街を歩き回る現象になった。 他にもデジタルガジェット大手のグーグルは、メガネタイプのAR機器グーグルグラスを開発し、 自社の地図情報(グーグルマップ)などと連携して視界に映る建物のデータを表示したり、 その日のスケジュールを視界の中に出現させるという使い方を可能にしている。 過去のSFでよく表現された「サングラス内にデータが出る」アレをリアルにやるわけである。 カーナビゲーションの発展型のアイデアであるとも言えるわけだが、 電子情報や2次元情報が「現実世界の中にさりげなく割り込む」時代が来ているのだ。 202110追記……デジタル世界の進化は本当に目覚ましい。 『ポケモンGO』に代表されるAR(拡張現実)が生活に入り込んでから数年ほどが経ったが、 これらのテクノロジーを更に進化させた“XR”なるジャンルが今、注目を浴びている。 仮想現実(VR)のビジュアルを現実世界と重ね合わせるのがいわゆるARであるが、 このビジュアルを「重ね合わせるだけでなく統合的に制御する」方法論が登場しているのだ。 XR技術の多くは2021年現在のところまだ研究段階であるが、2020年代中には現実となるだろう。 例えばデジタルメガネ(グーグルグラス等)にインターネットの情報を投影し、 町歩きの際に交通案内をしたりスケジュール管理するサービスが既に始まっているが、 これを更に進めて、「メガネを通して投影された映像を自分で操作したり情報共有する」など、 まさに「AR情報をリアルタイムの生活の中で様々な道具として利用する」ことが可能だという。 デジタルメガネがPCディスプレイやスマートフォンに代わる映像メディアとなり、 そこに「風景と同化した状態で広告を表示したりする」ことも可能になるというのである。 XR技術の駆使によって、まさに「現実世界と電脳世界が混じり合う」ことになるわけであるが、 ユヴァル・ノア・ハラリが“予言”した、“ホモ・デウス”の入口を見ているような気分だ。 ホモ・デウスというのは簡単に言えば「テクノロジーの進化で万能になった人間」のことであり、 その選択を受け入れる人とそうでない人の“格差”は種族の違いほど大きくなるという。 (この“兆候”は既に、デジタル機器を使える人と使えない人のギャップとして顕在化している) まさしく『攻殻機動隊』や『マトリックス』の世界を地で行く風景をユヴァルは見ているようだ。 そしてXR技術が作り出す未来予想図も、こうしたSF世界とよく似ているのである。 興味深いのは、「町中至る所に立体映像が表示される」ようなSF世界の具現化も、 XR技術を駆使することで、わざわざ物理的にホログラムメディアを作らずとも可能なことだ。 デジタルメガネを使うという条件下ではあるが、そこに“マルチウィンドウ表示”をすることで、 視覚的にはSF映画のワンシーンを地で行くライフスタイルが手に入るという理屈である。 またデジタルメディア使用という条件に限ることで、自然界への「光害」を抑えることも可能だ。 街明かりやネオンなどの光を最小限に抑えても、XRでそれを十分カバーできるのである。 デジタルメガネなどを使っていない人から見れば、XR技術を使いこなしている人たちは、 「何もない空間を手で触って情報を得ている超能力者」のように見えるかも知れない。 シュールな光景ではあるが、自然界の動物たちが人間には見えない波長の光を見られるように、 人間にも「動物には見えない世界を認識するスキル」があっても、それはそれで面白い。 現に『ポケモンGO』などはある意味で新しい町歩きのジャンルを作り出しており、 外から見れば時として異様な光景であるが、それもデジタル時代の象徴的な変化と言えるだろう。 |
|
| |
|
| ◆緊急地震速報/生死を分かち得る数秒の余裕をくれる魔法 | |
| 緊急地震速報は、2000年代に日本が運用を開始した防災システムの1つである。 強い揺れがやってくる数秒前に「強震を警告する」装置であるが、“地震予知”をしているのではなく、 地震波の種類を活用し「本番前に警報を送る」システムになっている。 専門的な話になるが、地震波には複数の種類があり、その種類によって性質が様々に異なっている。 緊急地震速報に使われるのは、岩盤内を伝播する速度が最も早いP波であり、 「最も強い揺れ」をもたらすS波はこれに遅れてやってくることが地震学ではすでに分かっている。 そのためP波を検知して警報を発すれば、「強い揺れに遭遇する前に身を守れる」理屈になるのである。 大きな海底地震などで、大揺れが来る前にカタカタ、という“初期微動”を感じることがあるが、 これがP波の揺れであり、震源が遠い大きな地震ほど、S波とのタイムラグが大きいのだ。 わずか数秒の差ではあるが、「不意打ちで大揺れを食らう」可能性を考えれば、 とっさに身を守ったり、覚悟を決めて身構える心の準備をさせてくれるわけだから心強いと言えるだろう。 調理中であれば、その数秒でガスコンロの火を消し止めるくらいは出来るはずだし、 大揺れに翻弄される前に机の下などに待避することも出来る理屈になる。 地震予知そのものではないが、地震発生直後でもそういう警報が出せるのはある意味凄いことだ。 「これから強震が来ます」と言ってくれる警報器が出来るなど、数十年前には想像も出来なかったろう。 ただし「実際に発生する地震波を検知」する警報システムである以上、弱点もある。 例えば複数の震源でほぼ同時に地震が発生した場合、誤作動を起こす可能性があり得ることだ。 東日本大震災をもたらした東北地方太平洋沖地震の際にも起きており、 別所で同時発生した2つの小さな地震を「1つの大地震」と誤解して警報を出してしまったケースもある。 また直下型地震の場合、P波とS波のタイムラグが少ないため、 緊急地震速報と同時に強震に襲われたり、最悪の場合「速報の方が遅い」ことさえあるのだ。 これはまさしく、地震予知ではないからこその弱点であり、限界であるとも言えるだろう。 地震波を検知してからマグニチュードを計算し、震度を推測するのも「一瞬ではない」らしく、 数秒ほどはどうしてもかかってしまうため、震源が近い地震では「警報が間に合わない」こともある。 それでもその数秒の“余裕”を与えてくれるシステムを、筆者は評価したい。 |
|
| |
|
| ◆空調服/持ち歩く扇風機や着る扇風機を使う時代が来た(ハンディファンの解説を含む) | |
| 空調服は、日本生まれの個性的な“家電製品”である。 欧米人も時として音を上げる、高温多湿の日本の夏に外で作業を強いられる、 土木作業員や工場勤務者などを対象に開発された製品であり、 化学繊維製のジャケットの脇腹の部分に2基のファンが設置されており、 ジャケット内に空気を循環させることで、体感温度を下げる効果があるという。 常に扇風機の風に、上半身が当たっているような状態なわけだ。 21世紀に入ってから出てきたアイテムで、今や工事現場の日常風景となり、 イベント会場のガードマンなどが着ていることも時々SNSで話題に上がる。 真夏でも長袖という風貌で一見して暑そうに見えるのだが、 あの構造だからファンの風が外部に逃げることなく循環可能なのである。 元々作業員向けのアイテムだが、一般人が購入することもいちおうは可能だ。 筆者も街中で普段着の青年が着ているのを見たことがある。 (また最近だと、訪日外国人観光客が買って帰るケースもあるようである) 今(2020年代)となっては日常風景の1つとなっているが、 「扇風機を着用して作業する」など、1昔前ならSFの発想だっただろう。 SNSでは『バック・トゥ・ザ・フューチャー2』と関連付けた意見もあった。 (思えば『バック2』の設定年代は2015年で今はもうその時代より未来なのだ^^;) メカニカルな製品を「身につけて」生活するという近未来的なアイデアを、 日本が世界に先駆けて開発し、流通させているというのも興味深い。 同じく「持ち歩く扇風機」ハンディファンも今や日常的なアイテムだろう。 見た目はオモチャのように小さな機械だが、あれで結構涼しくなるから面白い。 冷房ではないが、風が常に吹き抜けるため熱が籠もるのを防いでくれる理屈だ。 首に引っ掛けて両側から顔に風を当てるネッククーラータイプもあり、 実は筆者も愛用してたりする(手に持たずに済むため楽なのだ^^;) 冷房するわけではないが、電動の団扇のようなもので「ないよりマシ」なのだ。 空調服の先進性に目を留めた海外SNSでは、海外展開を期待する声もある。 地球温暖化などの気候変動を背景に、猛暑や干魃がより激化すると言われる今、 こうしたアイテムが「生活圏の維持に欠かせなくなる」可能性があるという。 筆者も環境問題や気候変動の問題に対しては、ただ規制するばかりではなくて、 変わっていく環境に「適応する方法を模索する」ことも大事だと考えるので、 空調服のようなアイデアに期待するところもあるのである。 |
|
| |
|
| ◆デジタルサイネージ/動く看板という近未来風景(デジタルペーパーの解説を含む) | |
| デジタルサイネージは、街角や駅構内、列車内などに設置される看板の1種だ。 液晶パネルや有機ELフィルムを使った、大画面ディスプレイの1種だが、 企業広告やCMを流すために使われることが多く、今や日常風景と化している。 「動く看板」というアイデア自体は、数十年前から電光掲示板などであるが、 それが大規模な設備ではなく、家庭用TVくらいのサイズにコンパクト化して、 街中至る所で見られる時代になっているという点が面白いと思う。 大阪や東京などの大規模ターミナル駅では、のぼりの旗のように並べられ、 道行く人に新たなイベントやキャンペーンの宣伝を繰り返す風景が見られる。 従来の電光掲示板と違って縦長のレイアウトでも使えるのも特徴の1つで、 縦長のディスプレイ内を区切って、複数の映像を同時に流すことも可能である。 もちろんアナログ看板のように、職員がポスターを交換する必要もないのだ。 1990年代半ばに公開されたSF映画『トータル・リコール』では、 地下鉄の出入り口の横にTV画面が並ぶという近未来デザインが登場したが、 私たちは今やこれと全く同じ風景を日常的に見ていることに気付く。 (『トータル〜』は2060年代の物語だから、数十年早く実現したことになる) 1990年代でもやろうと思えば出来た(実際映画のセットに使われた)だろうが、 コストパフォーマンス面でも問題ない時代が実際に来たわけである。 更に将来的には、高輝度デジタルペーパー(下記)などを使うことによって、 今よりも更に薄くコンパクトに洗練されたサイネージが出てくるかも知れない。 それこそ旗のように「風で揺れる」くらい薄くすることも技術的には可能だ。 現在のデジタルサイネージは液晶ディスプレイの延長線に当たるため、 強風や地震で落下などしたら結構危ないシロモノでもあるが、 デジタルペーパー方式ならこうした落下リスクも軽減することが可能だろう。 因みにデジタルペーパー自体も20世紀には近未来アイテムと言われたが、 現在既に実用化しており、ただしTV画面のように高輝度なものは発展途上だ。 しかしデジタルペーパーの素材候補の1つでもある有機ELフィルムが、 スマホ画面に使えるくらい明るく表示出来る時代にはなってるため、 (ただしスマホの場合、筐体にバックライトを仕込んでる場合が多いのだが) 「紙のように薄くても明るいデジタルペーパー」もあり得るとは思うのだ。 バックライト不要の高輝度デジタルペーパーの技術が確立すれば、 映像メディアの世界はまた1段階、大きく飛翔することになるような気がする。 上にも書いたように、「旗のような映像メディア」が作れるからだ。 見た目のSF感だけでなく、軽量のため事故リスクも少ない理屈であり、 本当に下敷きのように薄いディスプレイが日常になる可能性があるのである。 (今でも結構薄くはなっているが、下敷きレベルには至っていない) |
|
| |
|
| ◆プロジェクターマッピング/映像投影技術がもたらす新たな可能性 | |
| プロジェクターというアイテムは、元々はスクリーンなどにスライドを投影する電子機器であった。 ところがしばらく前から、スライドのような静止画ではなく、動画を投影できるタイプが登場し、 (映画の投影機=映写機は戦前からあったわけなので、技術ベース自体は古いのだろう) これを企画プレゼンテーションのような営業活動だけではなく、 それ自体を新たなエンターテイメントのジャンルにしてしまったのがプロジェクターマッピングである。 文化財の壁に幻想的な映像を投影するイベントは昨今、すでに余り珍しいものではないだろう。 その文脈において、プロジェクターマッピングそれ自体は必ずしも“未来都市点描”のテーマではないが、 最近このアイテムが新たな技術的発展をし、それを活かした演出をするようになっているのだ。 それは「リアルタイムの現実世界と呼応できる」タイプの登場を意味する。 広義のAR(拡張現実)と呼んでも良いかも知れない。 従来のプロジェクターマッピングはあくまでも、映画のように映像を投影するものでしかなかったが、 最近「舞台俳優やスタッフとリアルタイムに呼応し合う」技術が実用化されているのだ。 例えば企業プレゼンではスクリーンやテーブルに投影した映像を、そのままタッチパネルのように操作し、 イベントでは「舞台俳優と背景映像が共鳴し合う」演出が可能になっているのである。 筆者にとってこれは、ホログラフィ(立体映像)を初めて見た時に匹敵する驚きであった。 「ディスプレイをそのまま触って操作できる」タッチパネルもワクワクするが、それ以上のものだ。 (その後ホログラム式タッチパネルというアイデアが実際に登場して更に驚いた^^;) これはプロジェクター側に「現実世界の動きを認識できる」プログラムが搭載されたためである。 投影するスクリーンなどの映像に干渉する人の動きを識別し、反応するプログラムになっているため、 「アドリブの動きにも対応する」ことが可能になっているらしいのだ。 映像自体は投影されたものなので、タッチパネルのように乱暴に扱って壊す心配もない。 イベントなら雰囲気を合わせるのみならず、舞台俳優の手足の動きに映像を沿わせることも可能だ。 アミューズメント施設では、施設の壁を「体感ゲーム」にするところもすでにある。 「テーブルにキーボードの映像を投影して操作するPC」というガジェットを発明した人がいるが、 これもこうしたAR系プロジェクターマッピングの応用なのだろう。 自動車のヘッドライトに組み込み、「カーナビのデータを路面に投影する」技術も開発されたそうだ。 今や映像スクリーンは、デコボコな面でない限り、どこでも代用できる時代なのである。 (平面に限らず、球面にマッピングした映像オブジェも存在する) 「箱庭風景を作れる砂場」という子供向け教材を作ったメーカーもある。 これは腰高サイズの小さな砂場なのだが、その砂の「形状を識別する」カメラが搭載されており、 その形状変化に合わせて、「擬似的な地形をマッピングする」ことが出来るようになっている。 砂場に穴を掘れば池や湖の映像を投影し、砂を盛れば木々が生い茂る山に変わるのだ。 これもアドリブ対応式のプロジェクターマッピング技術の応用と言えるだろう。 単なる子供向け玩具と侮るなかれ、環境問題教育のための教材としても使えると言われているのだ。 将来的にはコミュニケーションAIと組み合わせて、「2次元キャラと会話する」ことも可能になろう。 今でもそれを疑似体験できるロボットや映像メディアはあるが、その裾野が飛躍的に広がるのだ。 オフィスの壁などに投影され、業務をサポートする“電子秘書”が出てくるかも知れない。 それこそまさに『新スタートレック』に登場するホログラム・ドクターを地で行く世界である。 いやはや、何ともエキサイティングな時代になったものだ。 因みに筆者は、人間とコミュニケーションするAIは、人間そっくりである必要はないと考える。 人間そっくりの肌と顔を持つアンドロイドの研究をしている人もいるが、 こうした試みは意欲的であるものの、いわゆる“不気味の谷”に嵌まり込むリスクが高い。 どれだけ上手く作ったとしても「人間そのものではない」以上、返って警戒されるのではなかろうか。 筆者はむしろ2次元アニメのようなデフォルメデザインの方が「割り切れる」ように思うのだ。 あえて人型を外し、“ゆるキャラ”のようなデザインで登場させるのも選択肢の1つだろう。 それこそドラえもんのような外観の方が、不気味の谷に嵌まるリスクは低いと考えられるのである。 人間と全く同じ姿ではないからこそ、AIという「人外の知性」に慣れる訓練にもなるし、 ひいては人間の視野を広げる契機となる、というのは希望が過ぎるだろうか。 |
|
| |
|
| ◆ペロブスカイト太陽電池/ソーラーパネルの裾野を広げる大発明(全固体電池の解説を含む) | |
| ペロブスカイト太陽電池は、日本が開発に成功した次世代の光発電装置である。 2010年代に試作品が作られた後、2020年代に量産化の準備が始まっているとされており、 ソーラーパネル市場に“地殻変動”を起こすことが期待されている。 従来のシリコン主体のソーラーパネルと異なって、フィルム状になっているのが特徴で、 湾曲した壁や柱といった、曲面に貼り付けて使えるのが大きなポイントだ。 (加工も比較的容易なため、例えば瓦の表面に貼り付けるなんてことも出来そうである) 発電素子も従来のシリコンとは異なる新たな化学物質を使っているため、 量産ベースに乗せれば安価で普及させやすいと言われている。 ただ薄型であるためか、従来のソーラーパネルより耐用年数はやや短いようである。 業界では日本発祥のこの発明が“ノーベル賞クラス”とも言われているが、 「安価で量産させたら世界一」な中国が、猛烈に開発を追い上げていると言われており、 今後激烈なシェア競争が始まるのではないかという説もあるようだ。 ソーラーパネル市場は今、その中国の独壇場に近い(シェアの半分以上を占める)ため、 是非ともここは日本が主導して、新たな市場を切り拓いて欲しいところである。 因みに「完成品の安価な大量生産」では中国に後れを取っている日本であるが、 精密機械を支える高純度の化合物素材の開発と生産では、世界トップシェアでもある。 例えば半導体開発に欠かせない、フッ化水素やレジストといった素材のことだ。 中国や韓国も独自開発を進めているが、まだ日本の品質には追いつかないようである。 トヨタなどが開発を主導する全固体電池なども期待のホープだろう。 従来液体だった電解層を固体化しているため、液漏れトラブルが理論上起きない仕組みだ。 これが量産ベースに乗れば、バッテリー市場などにも革命が起きると言われている。 |
|
| |
|
| ◆ホログラムボタン/ついにやって来たSF映画の日常風景 | |
| ホログラムボタンは、車両ミラーメイカーの村上開明堂社が開発した次世代操作パネルである。 特殊なミラーを組み込んだ立体的な機器を使うことで、映像が空間に浮かび上がる原理を利用し、 (この特殊ミラーには村上社と提携する別のベンチャーが関わっているようである) 「空間に浮かび上がったボタンを操作できる」ようにするというアイデアなのだ。 実際にはそこに何か実体的なものが存在するわけではなく、目の錯覚を利用しているだけだが、 操作型プロジェクターマッピングと同じ要領で、指の動きを赤外線センサーが感知するらしい。 SF映画の世界では結構ポピュラーに見られるホログラフィ=立体映像の技術はハイテクの塊だ。 従来の映像技術が基本的には全てスクリーンやディスプレイ(モニター)を必要としたように、 「投影する実体」がなければ画像や映像を視覚的に表すことは物理的に出来ないのが常識である。 近年目覚しい発展を遂げるプロジェクターマッピングも、この法則からは逃れられない。 その“常識”を打ち破る基本的なアイデアは「目の錯覚」を利用することだ。 光の反射コントロールにより人間の視覚において、「結像点を手前に持ってくる」ことにより、 脳がその映像を「ディスプレイの手前に浮き上がっているように感じさせる」ことが出来るのだ。 その第1弾が、特殊な感光素材を用いた“ホログラム写真”であった。 完全に立体的とは言えないが、立体感を感じるキラキラした写真を見た人も少なくないだろう。 あれも基本的には光の反射をコントロールし、脳に錯覚を引き起こすアイデアなのである。 3Dメガネを用いた3D映画や映像アトラクションも、基本的な原理はこれと同じである。 映像技術自体の“立体加工”ではなく、3Dメガネとの併用ではあるが、 組み合わせることでやはり結像点をスクリーンの手前に引き寄せることで、立体感を感じさせる。 CG画像を組み合わせて立体物を擬似的に見せるステレオグラム画像も1時期流行った。 こちらは3Dメガネの代わりに「人間が自発的に結像点をコントロールする」技能が必要だが。 (だからコツを覚えるまでは立体的に見えないという困惑も多くの人が味わったろう^^;) そしてこのアイデアを「映像機器で実現しよう」という試みが、近年活発に行われているのだ。 映像ディスプレイ自体が光の反射をコントロールする必要があることから、 ディスプレイ自体が平面ではなく、3面鏡のような反射ミラーを組み込んだ立体的な機器であり、 スマートフォンのようにコンパクト化する段階には至っていないが、 折り畳みスマホの技術を応用すれば、いずれは携帯式立体映像メディアも可能なように思える。 (平面映像でも擬似的な厚みを感じさせる程度なら、今既に実用化しているらしい) そしてこのアイデアを更に1歩進めたのが、この「立体映像ボタン」なのである。 SF映画などでしばしば見られる「立体映像を直接触って操作する」という、 これまでCG合成でしかなし得なかった風景を、リアルに味わえる時代が到来しつつあるのだ。 コロナクライシスで“非接触”が推奨されている時代も後押ししているという指摘があるが、 まさに「人間が考えたことは全て実現する」と言ったジュール・ヴェルヌの言葉や、 「十分に発展した科学は魔法と区別が付かない」というアーサー・C・クラークの名言の体現だ。 考えても見て欲しい……空中に浮かび上がる半透明の文字盤を操作できるのだ。 目の錯覚を利用した映像技術という“種明かし”をされているから「あぁなるほど」と思えるが、 そういう情報を与えられなければ、こんな代物は“魔法”以外の何物でもない。 アニメなどで魔術師が空中に魔方陣を投影させる、あのアクションそのままである。 将来的にはそれこそテーマパークなどで、来場者が同じアクションを再現することも可能だろう。 (3Dメガネ側に立体映像技術を組み込んだアイテムも最近開発されているらしい) 4年後(本テキストは2021年作成)の大阪・関西万博辺りで是非お目にかかりたいものだ。 (2025年追記:大阪・関西万博に行ってきたが、見た範囲ではこういうアイテムは見られなかったorz) |
|