 |
★第2次 怪獣大戦争 第10章 統合ナンバー:EC-C20201(CE10) |
|
激戦が続くサイトα――南之島。
誘導電波によってこの島に定着した3体の怪獣――ラドン、アンギラス、ゴロザウルスと、
これに対峙する“侵略者”である2体のネオガイガン、計5体の巨大生物同士の大乱戦である。
数の上では侵略者が不利だが、この侵略者はサイボーグ化されており“疲れ知らず”だ。
万トン級のぶつかり合いに、地球怪獣側が次第に疲労の色を見せ始めてきた。
なまじ普通の動物より縄張りが広く、プライドが高いだけに簡単に引けないのだが、体は正直だ。
赤と青の侵略者――いや破壊者が攻撃の勢いを強めようとした時であった。
突如島の北東沖――青いネオガイガンや今や“玉砕”してしまったメガロが上陸してきた方向から、
青白い熱線が海面を突き破って、低角度で島内に向かって解き放たれてきた。
熱線は青いネオガイガンを直撃し、強力な防御シールドが有効であったにもかかわらず、
激しい衝撃を真横から受けた青いネオガイガンは、そのままなぎ倒されるように地に伏せた。
地下シェルターで監視カメラの映像を見ていたSACのクルーたちにも、それが見えている。
そしてそれが何を意味するのかも、彼らは分かっていた。
「今のは――“ヤツ”か!?」
「あんな攻撃が出来るのが他にいるか? ――言っただろ、ヤツが目を瞑るなんてあり得ないって」
|
第2次 怪獣大戦争
〜復讐者襲来〜
★ 第10章―第2次 怪獣大戦争 ★
|
◆第1話 怪獣王反撃
間もなく海面が津波のように大きく膨れ上がり、見覚えのある背ビレと黒い尾が海上に突き上げる。
全身から蒸気を吹き上げつつ、黒い巨体が海中から上体を起こし、名乗りを上げるように咆哮する。
ゴジラだ。
ハワイ沖でネオガイガンに敗退した後、ずっと“地球の敵”を追ってきたのである。
超音速で空を飛べるネオガイガンには付いていけないものの、諦める選択肢はなかったと見える。
また途中、米軍がネオガイガンを狙って引き起こした核爆発で放射能を浴びたことで、
前回の対決で奪われた体力もすっかり回復していたようである。
力が有り余っているのか、背ビレは熱線を放った後も、不気味に淡い輝きを放っていた。

怒りに満ちた低い唸り声を上げながら、ゴジラはゆっくりと上陸し、青いネオガイガンに迫る。
立ち込める土煙の中から起き上がったネオガイガンは、ゴジラに向かって鋭く吠えた。
再度吠え返すゴジラ……空気も緊迫し、もはや2頭の再戦を止めることは不可能に見えた。
身構えるゴジラとネオガイガン、間もなく両雄は真正面から睨み合う構図になった。
「こいつは……かなり怒ってるな。水中からぶちかますとか、中々しないぞあいつ」
「あの感じだと、海中で既に1戦交えていたみたいね、脇目も振らずに敵に向かっていったわよ」
「あるいはその時に1度負けたかもな、自分のテリトリーで後れを取るとか、かなり屈辱的な話だ」
「そりゃあ怒るよな……こいつは見物だぜ」
ゴジラの激しい怒りを察したアンギラスは、距離を取ってその様子を観察しようとその場を離れる。
「末永主任の敵を取ってくれゴジラ!」
「こだわるね……いや気持ちはよく分かるけど」
「それだけじゃないさ、あのゴジラは主任と何度か視線を交わしてただろ?」
エチオピア人職員ジョニー・アベディンの言葉に、宝田一郎は少し首を傾げる。
「SAC司令室の窓はマジックミラーだから、主任の顔は見えてなかったと思うけど……」
「けれど何度かこっちを見てたろ……その時1度だけ、主任とゴジラが同時に、軽く頷いたんだよ」
「ちょっと、それ本当なの?」
「確かにそんなことがあったね……偶然だと僕は思うけど」
苦笑する宝田……確かにSACがまだ侵略者に破壊される前、そういうことがあった。
SACの前を横切ってサイトαに上陸する時、ゴジラはいつもSACの方を睨んで警戒するのだが、
1度だけ、まるで末永やクルーに挨拶でもするかのように、軽く頭を下げたことがあったのである。
富士や谷沢が視察しに来る前の話だ……鳥居だったら知っているかも知れない。
「気の所為かも知れないけどさ……俺には主任とゴジラが理解し合っていた気がして仕方ないんだよ」
「怪獣と人類は理解し合えるのか……確かに遠大なテーマではあるけど……」
再びゴジラの背ビレが閃光を放ち、その口から青白い熱線が放たれた。
青いネオガイガンもゴジラに向けて、破壊光線を解き放つ。
今度は陸上で両者の熱線と光線が激突し、再び激しい爆発を起こした。
衝撃波が平野を突風と化して駆け巡り、爆発が上昇気流を起こして小さなキノコ雲を形作る。
衝撃波で揺れる監視カメラの映像を眺めながら、宝田は再び呟いた。
「ゴジラも……主任の無念が分かっていたっていうのか……?」
|
|
◆第2話 怪獣大戦勃発
侵略者に破壊され、今なお黒煙を噴き上げるSAC。
その沖合い――サイトαから見ればこちらは西岸だ――に、また大きなうねりが盛り上がった。
そして砕ける波頭の先から、金色の体毛に覆われた巨獣が姿を現す。
キングシーサーだ……沖縄からはるばる、フィリピン海を泳いできたようである。
キングシーサーは全身を震わせて海水を払い落とし、迷わずサイトαに上陸していく。
その視線の先には、何本も黒煙が立ち上っている……その真下が“運命の決戦地”であった。
キングシーサーにもモスラやメガロと同様“守護神”の矜持がある。
この島で起きていることが“世界の危機”であることを、恐らく分かっていたのだろう。
その2者は既に命を賭して散った……今自分が何をすべきなのかも、確信していたに違いない。
キングシーサーが“戦場”に到着すると、赤いネオガイガンの破壊光線を横から受けたゴジラが、
先制攻撃を食らった青いネオガイガン同様に、地響きを立てて倒れ込む瞬間だった。
さしもの怪獣王も、2頭のネオガイガンに戦術的に攻撃されれば、なす術はない。
何しろこの侵略者にはキングギドラにも匹敵する戦闘力があるのだ。
ゴジラは呻き声を上げながら起き上がるが、直撃を食らった片腕は今も煙を噴き上げている。
巡洋艦を1発で2枚に下ろしてしまうほどの威力だ、無理もない。
ゴロザウルスやアンギラスが包囲してはいるが、飛び道具がないが故に1押し足りない。
軽量級のラドンに至っては言わずもがなである……明らかに劣勢だった。
キングシーサーは1声吠えると、迷わず赤いネオガイガンに攻撃を仕掛けた。
この怪獣は“4つ脚”で駆けることが可能であり、その速度は新幹線をはるかに上回る。
そしてキングシーサーの参戦に気付いたゴロザウルスは、直感的に共闘すべきだと察したようで、
改めて赤いネオガイガンに向かって、猛然と突撃していった。
自然に揉まれたゴロザウルスには、敵意の矛先がどちらを向いているか、瞬時に感知できるのだ。
時速数百キロの巨大怪獣が2頭、それぞれ別方向から赤いネオガイガンに突進してきた。
ネオガイガンはほんの一瞬迷ったようだが、結果的にゴロザウルスに向かって破壊光線を放った。
破壊光線を逸らそうとゴロザウルスがネオガイガンから離脱したわずかな隙に、
大きく跳躍したキングシーサーが、背後から牙を剥いて飛び掛る。
しかしそれを察したネオガイガンは、反転して長大な尾をキングシーサーの横っ腹に直撃させた。
勢いのベクトルを捻じ曲げられたキングシーサーは、軽く100mは飛ばされて地に伏せる。

更に追撃しようとする赤いネオガイガンだが、その死角から今度はラドンが突っ込んできた。
軽量級だが、相当な高角度からの“急降下爆撃”は侮れるものではない。
腰を折るようにつんのめるネオガイガンは、パルスレーザーでラドンを牽制しながら堪えるが、
何とか体勢を立て直した時には、既に3頭の怪獣に包囲されていた。
激闘に拍車がかかり、見守るSACクルーにも、感嘆とも溜息とも取れない息が漏れる。
「すげぇ……!!」
「ゴジラとキングシーサーの参戦で一気に触発されたみたいね」
「これで5対2か、まさに“怪獣大戦”じゃないか……!」
形勢が変化したことを見計らってか、ゴジラが再び動き出した。
奇しくも対ガイガン戦でタッグを組んだアンギラスと、青いネオガイガンに再度攻撃を仕掛ける。
青いネオガイガンは再び破壊光線を発射したが、ゴジラも熱線を放って応戦する。
再び激しい爆発が起きたが、ゴジラはそのまま突進を続けた。
レーダーでゴジラの突撃をキャッチしたネオガイガンは、そのまま破壊光線の連射体勢に入った。
幾らゴジラでも熱線の短期連射はできないはずで、ネオガイガンの戦術は妥当に見える。
しかし立ち込める土煙の中から出現したゴジラは、かなりの前傾姿勢でネオガイガンに突進した。
青いネオガイガンがゴジラの“低空タックル”に照準を補正するよりも早く、
ゴジラの頭部が斜め下からネオガイガンのアゴを突き上げた。
その瞬間破壊光線が発射され、標的を失った光線が鋭く空を切り裂いて宇宙空間に飛び去る。

更にバランスを崩した青いネオガイガンを、横からアンギラスの巨体が押し倒しにかかった。
地響きと共に倒れ込むネオガイガン……どうやら“作戦”成功のようだ。
しかしアンギラスに押さえ込まれたネオガイガンを、ゴジラが更に攻撃しようとした瞬間、
別方向から飛んできた破壊光線が、アンギラスを再び強引に引き剥がした。
赤いネオガイガンが、数百m先からアンギラスを攻撃したのだ。
しかしその赤いネオガイガンに、ゴロザウルスとキングシーサーが左右から飛びかかる。
赤いネオガイガンは長い尾を振り回して牽制したが、さっきほど余裕がないのは明らかであり、
“重量級”2頭の参戦が状況を変えたことは間違いないようである。
まさに地球史上最大規模の“怪獣大戦”が、太平洋上の島――サイトαで展開されていた。
|
|
◆第3話 希望の真珠湾艦隊
その頃ハワイの真珠湾では、国連太平洋艦隊が出撃の準備を整えつつあった。
怪獣カプセル落下が起こした津波から立ち直った、あるいは生き延びた艦船を中心に体勢を立て直し、
これが初陣となる国連軍の新型戦艦“アーク”を新たなる旗艦として、
サイトαで暴れているネオガイガンを迎撃する試みだ。
ネオガイガンが形成する防御シールドがネックだが、といって手をこまねいているわけにも行かない。
国連軍の新型戦艦“アーク”は、全長222mのハイテク戦艦で、世界初の原子力推進戦艦でもあり、
2門の主砲はレールガンやメーサーに換装することができる。
最新鋭のイージス・システムも搭載され、艦隊の指揮を執るだけでなく電子戦にも対応し、
熱線・放射能退避室(耐爆シェルター)をも備えるなど“移動要塞”としての機能を付加されていた。
そしてアークには、改良されたGディフェンダーも搭載されていた。
試作機よりも出力を上げ、1つの島を包み込むほどの妨害電波を拡散しながら放射することが出来る。
放射電波の“有効射程距離”も、弾道ミサイル並みの1,000kmに達している。
改良に参加したのは、もちろん鳥居である。
サイトαで開発した怪獣誘導システムのノウハウが、改良型Gディフェンダーにも活かされていた。
しかも鳥居は、自らその制御役を買って出たのである。
出撃準備が整い、国連太平洋艦隊の兵士たちが、新造旗艦アークにも続々乗り込んでいく。
その中に、借り物の迷彩服に身を包んだ鳥居の姿があった。
背中に抱えた黒いバックパックには、Gディフェンダー制御に必要な資料が詰め込まれている。
Gディフェンダー搭載を見届け、アークに乗り込もうとする鳥居を、ふと背後からエリカが止めた。
「ねぇ……何故、あなたが行くの?……あなたは軍人じゃない、科学者なんでしょ?」
その表情には困惑と不安の色が浮かび上がっている。
科学技術の軍事利用にずっと懸念の意識を持ってきた人物が、自ら戦艦に乗り込もうとしているのだ。
しかもこの青年は、エリカが犯罪者になる可能性を、寸前で止めた恩人でもある。
「このシステムは、僕が改良したんだ。 だから僕が責任を取って管理しないと」
「……軍事に関心がないって言ってたあなたが……どうして?」
エリカの思いを汲み取った鳥居は、苦笑するような素振りで言葉をつなぐ。
「はは、今でも関心はないよ。 これは軍事利用じゃない……平和のための技術なんだ」
「……でも、悪用されないっていう保証はないわ」
「だから僕が管理するのさ、それが開発者の責任だと思う。 これは――僕にしかできないことなんだ」
鳥居の強い決意を察したエリカは、半ば諦めるように深い溜息を吐いた。
「そっか……神崎さんに影響されたのね」
「……あの人は僕の先輩だし、恩人だからね……神崎先輩がいなかったら、今の僕もいない。
あの人が命を賭けているのに、僕が何もしないわけには行かないよ」
そう言うと鳥居は、タラップを上がってアークに乗り込んだ。
エリカの後ろには連絡係を務めたUNA職員ハルトマンが立ち、感慨深そうな表情を浮かべている。
「ミスター鳥居、任せましたよ……どうかご無事で」
「……気をつけてね」
エリカとハルトマンに手を振った鳥居は、その奥に立つ富士会長に気付いた。
そして富士が今度は目を逸らさず、鳥居の目を見据えてしっかりと頷いたのを見た。
富士もまた科学の軍事利用に懸念を示してきた人物だ、それゆえ鳥居との間にはわだかまりもあった。
その富士が、鳥居の努力を認めた瞬間であった。
鳥居は、思わず富士に向かって頭を下げる。

最後の迎撃に向かって、国連太平洋艦隊の緊急臨時艦隊が真珠湾を出港して行く。
最新鋭の旗艦アークを中心に、ミサイル巡洋艦3隻、空母1隻、駆逐艦・潜水艦6隻の多国籍軍、
言わば“真珠湾連合艦隊”と呼ぶべきだろうか。
かつて悲劇的な戦渦の引き金を引いたこの湾から、今世界の希望を背負った連合艦隊が出撃した。
鳥居を見送っていたエリカは、隣に立った富士に気付いた。
富士に「冷たい」第1印象を持っていたエリカは、思わず目を逸らそうとする。
そのエリカに向かって、しかし富士は予想もしなかったセリフを口にした。
「……彼なら、きっとやってくれるだろう」
驚いて富士の顔を見上げたエリカに、富士は初めて優しい表情を見せた。
「私の甥だ、保証するよ」
|
|
◆第4話 復讐者の内紛
その頃――牢からの脱出に成功した神崎たちとザインは、艦内通路の分岐点にいた。
「よし、ここで2手に分かれよう――おい、あんた」
「……ザインだ」
「そうかい。 それじゃザイン、案内してくれ。 ヤマトはこいつらと格納庫へ」
「ちょっと待ってくれよマイケル、どうする気なんだ?」
「あの怪獣……ネオガイガンは、強いシールドを持っている。
どうもそいつのコントローラーが、この船のブリッジにあるらしい、解除しておくべきだろ?」
マイケルの“作戦”に、しかし神崎は難色を示す……相当にリスクが高い、無謀な作戦だからだ。
「2人でやる気か? 幾ら何でも無謀だ、ここは敵地の真っ只中だぞ」
「2人ではない……私の部下が協力するだろう」
ザインはそう言って、傍らに立つX星人の部下を示した。
脱出後、彼らが担当している通路を縫って、ここまでハンター星人の目を交わしてきている。
「……そりゃあ心強いな――でも、ホントに大丈夫なのか?」
「もし戻らなかったら、ためらわずに逃げろ」
「……おい死ぬ気か? やっぱり無茶だ」
「いいかヤマト、よく考えろ。 こいつは、誰かがやらなくちゃならないんだ……人類のために。
それにパイロットはお前しかいない、お前だけは死なせるわけには行かない」
「不安なコト言うなよ、きっと戻って来るよな?」
「お前は現実主義者なんだろ? 現実を見据えろ、大事なことだ」
「マイケル……」
その時、奥の通路から走る音が聞こえてきた。
緊張した神崎たちだが、その表情が間もなく微妙に変化した。
「あぁ良かった――みんな無事だったか!」
走ってきたのは、何と格納庫で“撃ち殺された”はずのマイケルの部下、スコットだったのだ。
パトリックたちは驚き、笑顔を浮かべるが、マイケルは困惑している。
スコットは携帯ロケット弾“AT4”を背負い、何故か大きなサングラスをかけていた。
「スコッティ――生きてたのか?」
「この通りですよ、隊長……実験台にされそうな所を、すんでで抜け出してやりました!」
「そいつは大したもんだな……それでそのダサいサングラスはどうした?」
「脱出する際にちょっと拝借したんですよ、戦利品が要るでしょ?」
その瞬間――ザインの表情が引きつったのを、マイケルは見逃さなかった。
「面白いジョークだ……じゃあ景気付けに、ちょっと俺たち海兵隊のモットーを言ってくれ」
その言葉に、サングラスをしたスコットは、戸惑うような表情を浮かべる。
「え? あぁ、えぇと……あれ、何だったかな、ど忘れしちまいまして」
「おいおい、それでも俺の部下か? 口癖みたいに出てくるだろう――“Semper Fortis”」
「あぁそうでした、Semper Fortis!」
だが次の瞬間――マイケルの目から感情が消えた……いや部下や神崎たちもである。
「馬鹿め――“Semper Fidelis”だ、このクソゴキブリ野郎が」
マイケルの言葉に、今度はスコットの表情が引きつった。
そしてすぐに、背負っていたAT4を構えようと持ち代えた――その時である。
特徴的な電子音と共に、その眉間を赤い光線が貫通した。
赤い光線に断ち切られたサングラスが廊下に落ち、不気味に変色した目が露になる。
そして間もなくスコットは脱力し、緑色の泡を吹いて倒れ伏した。
すぐにその皮膚が劣化し――黒光りするハンター兵のものに変わっていく。
スコットの遺体を“ユニフォーム”にした敵兵だったのだ――そして撃ったのはザインだ。
「ザイン……」
「お前の部下だったのは知ってる……批判なら受け止める」
「いや、構わねぇさ、途中からおかしいと思ってた……これでやっとスコッティも浮かばれる」
そして倒れた敵兵から、ベンジャミンたちがAT4を接収する。
「奪ったものは、返してもらうぜ、ゴキブリさんよ」
「おい見ろよこいつ、前後逆に持っていやがる……取扱説明書も読めねぇのか」
「所詮ゴキブリだからな」
そんなやり取りを、神崎が複雑な表情で眺めている。
「“Semper Fortis”って確か、海軍のモットーだったよな?」
「ほぅ、よく知ってるなヤマト……ゴキブリ野郎が無知で助かったぜ」
「宇宙飛行士の訓練を一緒にした友人に、アメリカ海軍の出身者がいてね」
「まぁそういうことだ……パトリック、そのナイフは俺に寄越せ、ちょっと使い道がある」
そう言って、マイケルは部下からAT4に備えてた銃剣を受け取り、神崎に向き直った。
「きっと戻る、だからいつでも飛べるようにしておけ。 さぁ、行くんだ!」
改めて――通路を艦橋に向かって走りながら、マイケルはザインに話しかけた。
「……しかし俺も、まさかX星人と共同作戦を取るとは思ってなかったよ……聞いてるか?」
「……口数の多いヤツだな」
「悪かったな、俺の性格だよ!」
「……運命とは皮肉なものだ、計算通りにならない」
「だから面白いんだよ」
「……面白いか、なるほどな……面白い考え方だ」
ザインの何気ないセリフに、マイケルは走りながら思わず吹き出した。
「何だよザイン……ジョークも知ってるんじゃねぇか」
「……何がおかしい?」
「……い〜や、別に――おっと、急ごうぜ」
そして更に走る2人の前に、今度は有機的な曲面を持った大きな扉が現れた。
「……艦橋はそこじゃない、この先だ」
「この中は何だ?」
「武器庫だ」
「ほぉ、武器庫ね……少し、寄り道していいか?」
マイケルがそう言うと、ザインは表情を変えずに武器庫のロックを外した。
武器庫の中には、銀色のビーム拳銃や大型のライフルが置かれている。
そんな武器を眺めていたマイケルの視線が、ふと止まった。
「敵が追いついてくるぞ……そろそろ行くべきだ」
「分かってる……なぁザイン、先に機関室に案内してくれないか?」
「機関室? ……遠回りになるぞ。 ――まさか?」
再びザインの表情が微妙に変わった……どうやら、マイケルの意図に気付いたらしい。
「あぁ……いいコトを思いついた」
|
|
◆第5話 未来への選択
こちらはUNAホノルル基地の会議室。
“真珠湾連合艦隊”出撃後、再び臨時の国際会議が開催されたのだ。
ホノルル基地に来れない外国要人は、オンラインでTV参加する形式である。
決戦の艦隊が出撃したとは言え、何もすることがないわけではない。
もし作戦が上手く行かなかった場合に備えて、何か次の手を用意しておく必要があるし、
既に甚大な被害を被った戦災地の復旧や復興も、早急に実施しなければならない。
1国でどうにかなるレベルの被害ではないからだ……局地的な地域紛争の類とは次元が違う。
『敵は1箇所に集まっている。今核で叩けば、今度こそ撃破できる!』
開口一番、再びアメリカのロズウェル国防長官が“核攻撃案”を蒸し返した。
しかし先ほど1度は同調したソ連のザイエフ外相は、今度はこれに距離を置く姿勢を示す。
やはりソ連として、アメリカに主導権を握られたくはないからだ。
『ですがロズウェル長官……1度効かなかった兵器が、次は効くという確証があるので?』
もちろんこれで黙るほどロズウェルも簡単ではない……険しい表情を崩さずに、語気を強める。
『ザイエフ大臣、あなたもご存知のように、水中ではさしもの核兵器も破壊力は鈍ります。
しかし大気中なら、間違いなくダメージを与えられるはずです……どのみち他の兵器は通用しない。
あの“Gディフェンダー”とやらも、結局は無力だったのですからね』
「ロズウェル長官、結論には慎重であるべき――」
『富士会長、それで結果は出たのかね? 私にはそうは見えん……あなたの祖国も、今や瓦礫の山ではないか』
眉を潜める富士の言葉を途中で遮ると、ロズウェルは更に白熱してまくし立てた。
『ザイエフ大臣が協力すれば、多過ぎる核弾頭を一気に減らせる、そして厄介な怪獣共もいなくなる……
一石二鳥、いや一石三鳥ではありませんか!』
好戦的なロズウェルの主張に、会議室とTVがにわかにざわついた。
そして間もなく、中南米を代表して参加したブラジルの外交官が、これに異論を唱えた。
『ちょっと待って頂きたい……長官は太平洋の中央で大規模な大気圏核爆発を起こすというのですか?
……そんな事をすれば、大量の死の灰が中南米に流れることになります!』
「貴重な熱帯雨林が、広範囲で危機にさらされる恐れも高いですね」
『そう、まさに富士会長の言葉の通りです……長官は、途上国はどうなってもいいと言われるのか?』
中南米やアフリカは、白人列強の植民地支配を受けてきた歴史がある。
アメリカと冷戦状態にあるソ連とは違う意味で、欧米に主導権を握られたくはないし、
「世界の危機のため」に犠牲を強いられるのはごめんだと思っているのだ……当然の反応だろう。
アフリカ代表枠で参加した南アフリカの大使も、TVの向こうで頷いている。
太平洋で核爆発が起きても、すぐにアフリカが被災するわけではないものの、決して無害ではない。
核爆発の規模次第では、死の灰の汚染が中南米に留まらないことは確実だからだ。
「だが今叩けば、世界への打撃は最小限に抑えられるのでは?」
その1方、ホノルル基地にいる中国の王大使は、核攻撃も1理あるとの立場のようだ。
アメリカに主導権を握られたくはないが、黙っているのも得策ではないという狙いがあるのだろう。
既に母国が大被害を被った後ということもあり、もう失うものはないという思いもありそうだ。
『しかし大規模な核爆発が起これば、世界に波及する可能性が高いでしょう』
こちらはヨーロッパ代表で参加したドイツの大使だ……欧州諸国は環境問題に敏感である。
激論必至の中で、しかし“火種”を投下した等のロズウェルはまだ冷めていない。
『ではこのまま、エイリアン共に攻め滅ぼされるのを待てとでも?』
「ロズウェル長官、落ち着いてください……我々とて、何もしないのが良いとは言っておりません。
現に先ほど、太平洋艦隊も出撃させたわけですからね」
あくまでも「核攻撃ありき」で話を進めようとするロズウェルに、今度はパウエル将軍が釘を刺す。
貪欲で攻撃的な政治家が世界秩序を振り回すのは、軍人にとって面倒なことでしかない。
国防長官と言えど、制服軍人に比べれば軍事の専門家とは言えないものである。
『だがシールドが破れないのなら、幾ら攻撃しても無駄骨じゃないのかね?』
『それを言えば、核でも同じはないですか、ロズウェル長官?』
『通常兵器よりはマシでしょう、ザイエフ大臣……今現在、核に勝る“力”は地球上には存在しない。
その力を試すことさえ、許されないと仰るのですか?』
『試した結果もたらされる弊害が大きいからこそ、ここで議論になっているのではないのですか?』
疑問を呈するザイエフにロズウェルが反論し、そこにブラジルの外交官が釘を刺し返す。
既に甚大な被害を受けた中国や、プライドをズタズタにされたアメリカは報復したくてたまらない。
けれどもそれ以外の国にとっては、シワ寄せで受けるダメージを危惧せずにはいられないのだ。
どうも話が平行線になりそうだと思った富士は、現状の説明で余分な熱気を冷やそうと試みる。
「シールドについてですが……現在、より強力なGディフェンダーを新型戦艦に搭載し、
効果を探っています……もし十分大きな力なら効果があるというなら、希望はあると思われますが」
甚大な被害を受けたのは日本も同じだが、好戦的な報復だけが答えだとは、富士は考えていない。
敵を殲滅するという目的だけが1人歩きすれば、行き着く先は破滅しかないという懸念があるからだ。
怪獣という脅威に翻弄されながら、日本が核を保有しなかったのもその1つである。
富士に牽制されたロズウェルは、見下すような目つきで小さく笑った。
『それは皮肉かね、会長殿?……まぁいい、せいぜい対策を練ればいい……私はいつでも待っている』
|
|
◆第6話 復讐者の敗北
戦闘空母の艦橋に侵入したマイケルとザインは、ゾルクがいないことを確認し、操作盤の前に立った。
操作盤は有機的な配置だが、マイケルはザインの指示通りに、シールド発生装置のレバーを下ろす。
しかし――何の変化も起きない。
「……おい、何も起きないぞ、本当にこれでいいのか?」
「む、おかしい……こんなはずはないんだが…… まさか?」
「そのまさかだよ」
2人が振り向くと、艦橋の入口に司令官ゾルクがビーム拳銃を構えて立っていた。
「嫌な予感というのは当たるものだな、こうなると思ってレバーには工作を施しておいた。
つまりシールドの解除は不可能だ、また計算外だったようだなぁ?」
「ゾルク……!」
ゾルクは銃を構えたまま、不敵に笑いながら艦橋に入ってきた。
「おっと、動くなよ……その銃も捨てろ――しかし、キミ達人間は実に愚かな生き物だよ」
「何が言いたい、このゴキブリ野郎」
「我々がせっかく平和をもたらそうとしているのに、自由とかいう下らない幻想のために滅びを選ぶ」
「――自由が幻想だと?」
「そうとも、自由を求めて人間は争うからだ……実に愚かではないか」
嘲笑うようなゾルクのマウントに、マイケルは吐き捨てるように言い返す。
「……独裁者によって支配されるよりかはマシだ」
「だから幼いのだよ……お前は平和というのがどういうことか、まるで分かっていないようだ。
平和の達成には、強大なる力による“絶対的な支配”が必要なのだ」
「その“強大なる力”とやらで、俺達人間を押さえ付けるというのか、笑わせるな!」
「少なくとも争いは起きぬ……それが平和というものだ、まぁ人間共には永久に理解出来ぬかな?」
「力で押さえ付けるヤツは、より大きな力でいつか必ず滅びるぞ」
「ふふ、だから我々が存在するのだよ……絶対の平和をもたらす永遠の覇者としてな。
さて――お前たちにはここで死んで頂こうか。 心配は要らない、仲間もすぐに後を追わせよう」
そう言ってゾルクが銃を撃とうとした時、突然ザインが大声を上げてゾルクに飛びかかった。
ゾルクはすかさずザインを撃ったが、撃たれたザインはなおも前に進もうとする。
「バカなことを……ついに気が振れたか」
ゾルクはポケットから小さな円盤を出し、鬼のような形相で迫るザインの前にかざす。
円盤からサイレンのような音が響き、ザインはうめき声を上げて倒れ込んだ。
サイレンのような音は、かつて地球人がX星人を退けた“殺人音波”と同じ性質の音波だった。
撃たれた痛みと“殺人音波”にもだえ苦しむザインを、ゾルクは再び嘲笑う。
「はっはっは――だから人間は愚かなのだ……死ぬまで力の差を認めようとしない!」
そしてゾルクは、更に数発の光線を放つ――ザインは赤い血を吐き、仰け反るように倒れ込んだ。
マイケルは怒りの声を上げ、ゾルクに飛びかかる。
「――貴様ぁっ!!」
ゾルクはマイケルにも銃を発射したが、マイケルは後ろ手に持っていたナイフで光線を弾くと、
ゾルクとの間合いを一気に詰め、そのナイフでゾルクの左肩をぶすりと刺した。
刺されたゾルクは一瞬顔色を変えたが――すぐに冷酷な表情に戻ってマイケルを睨み付ける。
「ぐっ!?……ふん――笑止!!」
ゾルクは腰から“隠しツメ”を引き出し、マイケルの脇腹を切り裂いた。
痛みにひるんだマイケルに向かって放たれたゾルクの光線は、今度は彼の肩を至近で撃ち抜く。
「我々の関節が弱いことを見抜いた点は褒めてやる……だが隠しツメは知らなかっただろう!」
ゾルクが止めを刺そうとした時、ザインが死に物狂いでしがみついてきた。
「まだ生きていたか老いぼれ……ええい、放せ!!」
「私が食い止める、お前は行け! ……“人間”を、人間の未来を頼む!!」
マイケルは1瞬ためらったが、すぐに切り返して艦橋を後にした。
ゾルクは隠しツメでザインの胸を刺し貫き、彼の息の根を今度こそ完全に止める。
「地獄に堕ちるがいい、下等生物め……我々に逆らった代償だ」
「地獄に……堕ちるのは……貴様ら……だ――」
その頃――神崎たちは、格納庫でハンター兵たちと激しい銃撃戦を展開していた。
格納庫に置かれた円盤を盾にしながら、4人は少しずつSY−2へと近づいていく。
途中神崎は、神崎らと同じようにハンター兵に抵抗し、銃撃戦を展開するX星人たちを見かけた。
激しい白兵戦には慣れていないX星人たちは、1人また1人とハンター兵に撃ち殺されていく。
格納庫上部のデッキにも数人のハンター兵が立ち、光線ライフルで狙撃していた。
神崎は反射的に銃を構え、反対方向からX星人を攻撃する、ハンター星人の歩兵集団を撃った。
神崎の銃はハンター兵を倒せなかったが、こちらを向いた刹那の間合いのうちに、
ベンジャミンが神崎の横で、肩に担いだAT4の引き金を引く。
「そらゴキブリ野郎共、スコッティの代わりに特大の殺虫剤をお見舞いしてやるぜ!」
発射されたロケット弾は超低空で円盤群の横を飛び抜け、押し寄せるハンター兵団を直撃した。
至近で起きた爆発は“関節が弱い”甲板上のハンター兵たちを、文字通り一掃することになった。
何体かは軽やかに跳躍して爆風を回避したが、直後に頭部を撃ち抜かれて倒れる。
パトリックとカークが途中で盗んだ光線銃を構えて、神崎の後ろで満足げな表情を見せた。
神崎に助けられたことを知ったX星人は意外そうな表情を浮かべた。
すると今度は、SY−2に乗り込もうとする4人を、上部デッキからハンター兵の光線が襲った。
神崎らが防戦していると、今度は先ほど助けたX星人が、デッキに光線を放って神崎らを援護したのである。
その隙に、4人は素早くタラップを駆け上がって、何とかSY−2へと乗り込むことが出来た。
1方――負傷でよろめきながら通路を走り続けるマイケルを、突然斜め上から光線が襲った。
光線はマイケルの片足を撃ち抜き、倒れ込んだマイケルの前に、左半身が崩れたゾルクが現れた。
「たかが下等生物ごときを、この私が逃がすと思ったか!!」
マイケルは足を引きずって後ずさりするが、ゾルクは容赦なく光線銃を撃った。
すでに避ける余力のないマイケルの腕を、赤い光線が再び貫通する。
通路の壁により掛かって倒れかけたマイケルに、鬼の形相のゾルクが上部デッキから降りてきた。
「やはりザインなどに任せたのがマズかった……たかが地球人ごときにここまで手こずるとはな」
「ち……不本意だが……これでは、道連れも止むを得ないかな?」
「ふん……笑わせるな、貴様はもう何もできないハズだ」
「……あぁ、そう言えば俺も前に、あんたの部下にそう言ったよ……
けどアイツは、最後にとんでもないことをしてくれた――おかげで随分と参考になったよ」
「……何が言いたい?」
その時、轟音と共に空母全体が大きく揺れた――ゾルクが表情を変える。
「何だ、この音は……貴様、何をした?」
「あんたの部下と同じことさ……艦橋に来る前に、機関室に爆弾を仕掛けておいた」
その時正に戦闘空母のエンジンが火を噴き、空母は徐々に月面に向かって高度を下げつつあった。
マイケルはサイトSを破壊したあのアンモナイト型爆弾を武器庫から盗み出し、
ザインから操作を教わって、艦橋に来る前に機関室に仕掛けていたのだ。
「……貴様……よ、よくも私の船を……!」
「あんたは、人間を見くびった……結局はそれが敗因ってことさ」
その言葉に触発されたゾルクは、変色した目をかっと見開いてマイケルの胸に光線を撃ち込んだ。
薄笑みを浮かべたまま、マイケルもまた通路の壁に背中を預け、崩れ落ちる。
「……敗因だと、ふざけるな……我々が負けるハズがない――負けるハズがぁあぁぁ!!」
次の瞬間、爆発が連鎖的に発生し、ゾルクは絶叫と共に炎に包まれた。
機関室爆発による強震は、今正に脱出準備を完了しつつあった神崎らも感じた。
神崎は、直感的にマイケルの危機を悟った。
「ミスター神崎……もうこの船もダメだ、脱出しよう」
「そんな、マイケルは……隊長は?……彼を置いて行けるもんか」
そうこうしている内に、地響きと共に天井パネルの1部が崩れ、数隻の円盤が空母を離脱していく。
「……行こう、ヤマト……隊長がそう言ったんだ……間に合わなかったらそのまま行けと」
「もう行くしかないですよ……これ以上、俺達に出来ることはない」
神崎は血が滲むほどギュッと唇を噛み締め、覚悟を決めたように操縦桿を握る。
ハッチを閉めたSY−2は徐々に浮上し、ホバリングしながら旋回し始めた。
プライドの高いハンター兵たちは、なおも上部デッキから断続的にビームを撃ってくる。
1部が機体に当たり、上部主兵装のフェアリングにも穴が開いていく。
「畜生……お前らいい加減にしやがれ!!」
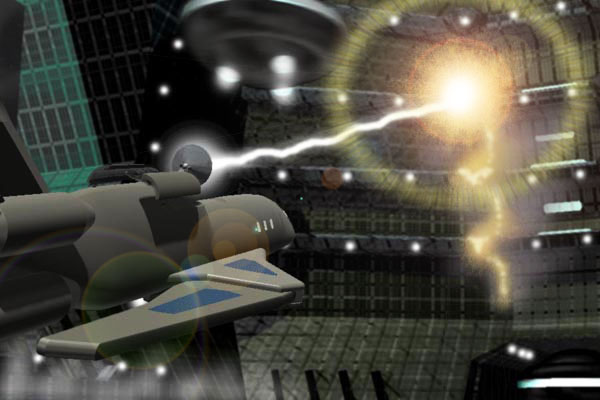
カークは思わずマイケルが座っていた席に滑り込み、マルチ・パラボラの光線発射レバーを握った。
SY−2から放たれたメーサー光線が、上部デッキを破壊し、狙撃兵を次々と撃破していく。
SY−2はその勢いのまま反転し、戦闘空母の外へと飛び出した。
推進力を失った戦闘空母は、あちこちから火を噴きながら、
離脱しようとするSY−2の下を、月の裏側の地表に向かって墜落していった。
そして数分後、戦闘空母は月面に激突し、激しい爆発と共に木っ端微塵に砕け散った。
月面に閃光がきらめき、オレンジ色の火の玉が衝撃波を放って、空高く膨れ上がっていく。
しかし神崎はそれを正視することも出来ずに、ただ無言で操縦桿を握り続ける。
だが無情にも――機体に複数の赤ランプが灯った。
「くそ……機体が安定しない、さっき被弾したからだ」
「何てこった……せっかく脱出できたのに、宇宙に神様はいないのかよ?」
「必ず生きて戻ると、隊長に約束したのに……」
仮に地球軌道まで何とか行けても、このまま大気圏に再突入すると空中分解し兼ねない。
絶望感に近い空気が漂い始めた、その時であった。
にわかに機体が安定し、推力データとは無関係にSY−2が加速し始めたのだ。
「なんだ……加速している、推力データには変化がないのに」
「……どうなってるんだ?」
『――聞こえるか? 地球の諸君』
間もなく通信機に、抑揚の小さな声が響いてきた……X星人特有のイントネーションである。
『貴公らの船を地球の大気圏まで曳航する……我々の艦長ザイン・ムーロイの命令だ』
神崎たちが思わず顔を見合わせたのは、言うまでもない。
|
|
| (第11章) |
|
【Meking Memo/設定補記】
2002年から2004年にかけて執筆(ただし完結は2005年頃だが)したエピソードを、2023年に再編したもの。
昭和のゴジラシリーズのサイドストーリーとして構想したエピソードの“旧作55〜60章”の再編版に当たる。
第7章の半ばまでは桂枝芽路氏が再編作業を担当していたが、8章以降はG-maによるため少し文体が違う(苦笑)
サイトαの“決戦場”にゴジラとキングシーサーが合流し、「怪獣バトルの役者が揃う」のと並行して、
ハンター星人の戦闘母艦でのアクションもクライマックスを迎えるのがこの章である。
ゴジラが“怪獣王”のポジションにあることは本作でも同じであるが、
「ゴジラだけを特別扱いしない」意図から、それほど突出したチート表現はしていない。
ゴジラを“神格化”しているファンには受けが悪いかも知れないが、これがG-ma流の「創作スタイル」である。
G-maは基本的に「主役と脇役を明確に区別化する描き方は好きではない」のだ。
ゴジラの“格”は尊重しながらも、他の怪獣にも出来るだけ見せ場を与えることを由とするのである。
その代わり、ゴジラにも旧作にないアクションを加えて個性化を図っている。
低空タックルで接近し、頭突きでネオガイガンの熱線を逸らすのもその1つである(笑)
元々プロレスを思わせるアクションは本家でもやっているわけだから、矛盾のある行動ではないと思う(汗)
キングシーサーが4脚で駆け回り、ネオガイガンを振り回すのも独自路線である。
“真珠湾連合艦隊”に鳥居が参加する展開は、『インデペンデンス・デイ(ID4)』へのオマージュが入っている。
ID4主役の1人である科学者のデヴィッド・レヴィンソンが、敵マザーシップ迎撃作戦に参加する下りだ。
本作の“原案”は1990年代後半に企画しているので、当時のSF作品にかなり影響を受けている(苦笑)
作戦機SY−2打ち上げシークエンスは『アルマゲドン』のX−72打ち上げシーンを意識しているし、
拿捕される流れの原風景が『スターウォーズ』にあることは前章も書いた通りだ。
ただ富士と鳥居の溝が埋まるシーンはオリジナルで、最初に立てたフラグを回収する狙いがある。
ハンター星人の母船がアンモナイト爆弾で破壊される展開も、中盤に立てたフラグの回収なのである。
なおハンター兵がスコットの遺体を使って攪乱作戦を仕掛けてくる展開は、桂枝芽路氏が提案したプロットである。
原文にはなく、単に艦橋に行くマイケルたちと格納庫に行く神崎たちが分かれる展開だけだったが、
本家ハンター人が“ユニフォーム”と呼んで人の皮を被っていたことをここで引っ掛けている。
反撃作戦で最初に殉職したスコットの出番を(中身は違うが)増やすことに加えて、
それに対峙する神崎たちやザインたちの動揺や怒りを強調する上で、印象的なシーンが増えることになった。
母船を脱出した手負いのSY−2を、X星人が支援する展開も再編後に追加したシーンである。
ザインの裏切りから和解のフラグが立った人類とX星人の関係に、プラスアルファがあっても良いと判断した。
戦闘でダメージを受けたSY−2が、何の障害もなく地球まで帰還するのもご都合的に思えたので、
「空中分解を防ぐためにザインの命でX星人が補佐する」というのもアリだと思えたのである。
実はSY−2が戦闘で破壊され、帰る手立てがない神崎たちが「X星人の円盤に便乗する」展開も後で考えたが、
“鷲の生還”というエピソードが消えてしまうために却下するという検討もあった(笑)
|





