 |
★SOT シリーズORGT 統合ナンバー:EA-ORGT22401N(N-ORGT001) |
|
「姉さん、見てください――もう始まってますよ」
シュビックの青年シェプル・エンティロンは、そう言って斜め上を指差した。
青空に伸び上がる数本のツル植物に、数人の人影がしがみついている。
ツル植物は何もない空間に垂直に伸びているように見えるが、実はそうではない。
ここは箱庭型バイオコロニーの境界壁であり、反射パネルで周囲の風景を投影することで、
圧迫感を感じにくいように設定されているのである。
恐らくアクロメリヒの亜種だろう、ツル植物は軽く1kmを越える高度まで伸びており、
その上空にかすかに見える「空の切れ目」でぷつりと切れるように止まっている。
この空の切れ目こそ、バイオコロニーの大気循環を制御するシステムがあるゾーンだ。
ツル植物とはいえ、ここまで伸びるケースは珍しいものだが、
大気圧や成分の変化に耐えて数千mも成長する、アクロメリヒなら可能な芸当なのだ。
原生地である惑星サニックでも、断崖絶壁を這うように空高く成長することで知られる。
「おーやってるねぇ、みんな体力あるなぁ」
シェプルに相槌を打つ女性の名はミーティオ・ヴェクニス。
古神族アーカトラスの血を引く混血で、身長2mを越えるなど結構な長身だが線は細い。
藍色に近い濃いパープルと、シルバーバイオレットのメッシュ髪も個性的だ。
定職に就かず放浪の旅を続ける“自称・冒険者”であるが、存外に手先は器用であり、
何をやっても大体普通以上にこなせるという“特技”を持っている。
……これで“方向音痴”じゃなけりゃ、パーフェクトなのだが。
ここはオルガーナゲイト・テクトラクタ内にあるオルファーマ・バイオコロニー。
人工的に農村環境を再現した中型のバイオコロニーであり、
内部に実際に複数の“人工農村地区”を内包している。
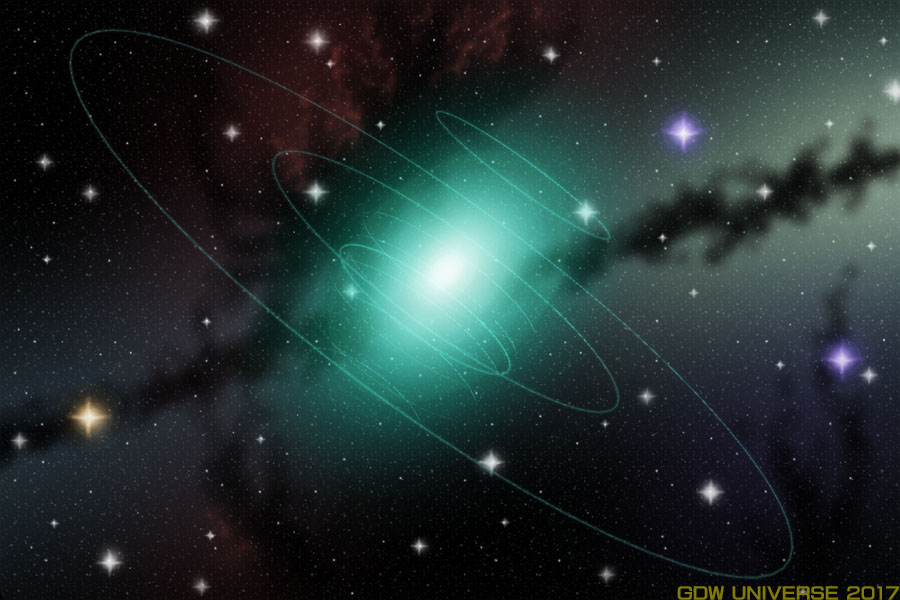
|
Spirits of Tracthizen
スピリッツ・オブ・トラクシズン――銀河市民の心得
≪シリーズORGT≫
★ 人工農村ソコルフォアの祭り ★
(想定年代:BWO002頃)
|
オルファーマ自治区の1角にある“人工農村”ソコルフォア地区。
この人工渓谷に囲まれた農村で3サイクルごとに行われるスポーツイベントが、
境界壁の大気循環システムまで伸びるアクロメリヒのツルをよじ登る、
ミラーウォール・クライミングである……単によじ登るだけでなくタイムトライアル式で、
時間を競う競技であるため、体力自慢の若者が能力を競い合うのに格好のイベントだ。
「あんな高度まで軽々と成長する……まさにアクロメリヒの特徴ですね」
「確かてっぺんまで上る時間を競うんだよね?」
「上位入賞者は30分を切るそうですよ、ザイオノイドか何かですかね?」
「力尽きて落ちるヤツがいるって聞いたことあるんだけど、それって大丈夫なの?」
「その答えはもう、出てるじゃないですかw」
ミーティオの問いに苦笑いを浮かべたシェプルは、端っこのツルの横の方を指差す。
そこに傘を上下逆にひっくり返したような黄色い物体が、ゆっくりと降りていく光景が。
「あれは“リパルサー・マット”かな?」
「多分そうでしょうね、落下した選手を受け止めて、地上まで運ぶのでしょう」
「……もしかして“あいつ”かな?」
「……姉さんが誰を想像したのか、もう分かりましたw」
再び苦笑いを浮かべたシェプルは、ミーティオと一緒に緩やかな坂道を上っていく。
坂道を登り切った人工丘陵の頂上が、ミラーウォール・クライミングのメイン会場であり、
その境界壁側に植えられた数株のアクロメリヒが、目も眩む高さまで伸びている。
2人が会場に到着するのと、リパルサー・マットが地表に接地するのが、ほぼ同時だった。
競技者の知人や看護師らしき人影が、リパルサー・マットを取り巻いている。
その中央に、黄色いリパルサー・マットに寝転がる、白黒の体毛の獣人が寝ていた。
半ば白目を剥いているその獣人に、看護師がボンベの酸素を吸わせている。
勢いで一気に上ろうとしたため、途中でブラックアウト状態になって失神したのである。
「あらミーティオ、久し振りね」
「おーおひさし、姉さんも来てたのね」
ミーティオが姉さんと呼ぶ、オレンジの長い毛に覆われた獣人はクルネア・ハーラム。
種族はミルシェプスで、シュビックのシェプルとは先輩と後輩の関係だ。
厳密に言うと、監視者アーカトラスの血を引くミーティオの方が年上なのだが、
クルネアはオルガーナ生命大学出身で、分野によってはミーティオを圧倒する博識なのだ。
まぁ――後輩のシェプルも、マニアックな知識の持ち主らしいが。
そして白目を剥いて伸びている獣人はキュベリオスのギータ・アストラス。
ここソコルフォア地区出身の青年で、かなりの熱血漢だが、やや暴走しやすい性格であり、
しばしば今回のように「裏目に出る」ことがある。
キュベリオスはスタミナに優れる種族だが、体力配分を間違えるとこうなるのだ。
「……やっぱり“彼”でしたね」
「懲りないよねぇ、これで何度目なんだかw」
その時――看護師に酸素吸入を受けていたギータが、意識を取り戻して飛び起きた。
「……はっ!? 何だ、どうなった、オレ今何位だ!?」
「失格じゃないですか? 落下したんですから」
「なっ、なんだってーーーー!!? 畜生、またかよっっ!!」
大袈裟に見えるリアクションで、頭を抱えるギータ……まぁ、彼はいつもこうなのだが。
会場の周囲には、複数のホログラムスクリーンが浮かび、試合の進捗を報じている。
トップグループと第2集団を追う、ドローンカメラの映像を投影しているようだ。
何しろトップグループは既に1,000m以上、上空にいるからだ。
目を凝らすと肉眼でも何とか見える高度ではあるが、豆粒のように小さい。
もし途中に低い雲でも浮いていたら、何も見えなかっただろう。
「体力配分考えないで、勢いで上るからじゃないの、バカねぇ」
「姉さんも容赦ないなw」
「こういう競技は体力とペースを相談しながらやるものよ、常識じゃないそのくらい」
冷静に突っ込むクルネアに、しょぼーんと項垂れるギータ。
ミルシェプスもまた、キュベリオスと同様にスタミナに定評ある種族である。
クルネア自身は試合にエントリーしていないが、こういう競技のコツは分かっている。
「ところで、今1位にいるのは誰です?」
「えぇと……どうもヴァルキアシスの選手みたいね、見かけない顔だわ」
「ヴァルキアシスもアスリート種族で有名ですよね」
シェプルやクルネアがそんな会話してると、ギータが起き上がって歩いてきた。
「……あの子、可愛いよなぁ♪」
「あの……彼は男子ですよ」
「ウソだろ!? 男子であの顔なのか!?」
「ヴァルキアシスは童顔が多いから、不自然じゃないわね……別に男子でも良いじゃない」
「出た、姉さんのジェンダーフリー論w」
「愛に境界はないわ……私は応援するわよ――あら、彼は?」
何を想像しているのか、ニヤニヤした笑みを浮かべてそう言ったクルネアだった――が。
ギータはもう、いなかった。
「逃げたわよ姉さん――ほんと、分かりやすい子よねぇw」
|
|
試合終了後――渓谷地区の中ほどにあるレストハウスで、昼食を採るミーティオらがいた。
人工的に作られたものとはいえ、高低差100mは軽くある渓谷地区の眺めは壮観であり、
鉱物から削り出したような繊細なアーチ橋が、両岸の小道を結びつけている。
惑星ゴルトンの伝統工芸をルーツとするゴルリーシェ様式のアーチ橋は、
それ自体がエアフライヤーの発着ターミナルであり、中ほどにレストハウスがあるのだ。
レストハウスの端は透明鋼の1種イグゼルコンで覆われ、谷底まで見通せる。
「あれ――ちょっと風景変わった?」
「そうですかね?」
そんな高所恐怖症が失神しそうなレストハウスの展望台で、ミーティオがふと呟いた。
シェプルは首を傾げる……リアルだが人工物である渓谷地区で、大きな変化はほとんどなく、
日常的にも余り聞かない言葉だったからだろう。
しかも彼女は筋金入りの方向音痴だ……別の場所と混同してるかも――と彼は思った……が。
「あら、よく気付いたわねミーティオ、観察眼あるじゃないの」
クルネアはそう言って再び意味深な笑みを浮かべた――シェプルは逆に目を剥く。
「えっ、本当に何か変わったんですか?」
「滝が1本増えたのよ……対岸に出来た水産加工施設の影響らしいわね」
そう言って、クルネアは渓谷の奥を指差す……そこに大小3本の滝が谷底に流れ落ちている。
どうも彼女が言うには……数年前にはここの滝は「2本だった」らしい。
「横の滝の水源から水道管を分岐させて、その排水の処理水を滝にしてるみたいよ」
「あーそっか、だからか……こんな所によくそんな工場作ろうと思ったわねぇ」
「見た目は辺境だけど、本質的には作り物だからね……ここは政府肝いりの研究区画だから、
既にある構造を利用した方が、合理的だと思ったんじゃないかしら」
「そっか……そーいやこの地区全体が、大きなプロジェクトなんだったっけ」
「あー言われてみればそうですね、オルガナ同盟行政庁のプロジェクトで作られたんですよね。
もう数万年も前のことだそうですが……」
思い出したようにそう言うシェプル……彼も何気にオルガーナ大卒の高学歴なのだ。
そしてその横で、ギータはわけが分からない顔をしている。
「お待ちどぉ〜、季節野菜のペザ・ヴァレスっすよ〜」
そこに料理の盆を載せた獣人の男性がやってきた。
タヌキに似た愛嬌のある顔は、シコイナーの雄性体であることを示している。
盆の上には薄い円盤状の生地に具を載せた“ペザ・ヴァレス”が白い湯気を上げている。
「おや君たち、ちゃんと仕事を始めたのですね、偉いです」
「失礼だなおめぇ、前に来た時からやってるんだぞ、バカにすんな」
シェプルの言葉に突っ込んだシコイナーの青年の名はスジーノ・ラッシュ。
放浪の大道芸人であり、ファストフード店のアルバイトもよくやっているらしい。
3人兄弟の長男で、手持ちのマジック芸をレストランなどで披露したりすることもある。
昔はスラムのチンピラのメンバーで、スリなどをやったこともあるらしいが。
「……なぁコレ、野菜しか載ってねーの?」
「アトラッシュの佃煮も載ってるっすよ、細かく砕いてるから目立たねぇっすけどね」
「……なんか物足りねぇなぁ」
スジーノが持ってきたペザ・ヴァレスを眺めて1人ぼやくギータ。
因みにアトラッシュというのは食用の大型魚類のことである。
そんなギータに、ミーティオが助け船を出す。
「物足りないんだったら、後で別の料理頼めば良いじゃん、向こうに何かあったわよ」
「そうっすねぇ、何ならここから飛び降りたら、真下に餌場あるっすよw」
「をぃ冗談じゃねぇ、オレを殺す気かよっ!?」
スジーノの弄りに、今度はギータが引く番だった。
何しろこのレストハウスはアーチ橋の中央部、谷底から100m近い高さにあるのだ。
熱血天然なギータにも、流石にここからロープなしで飛び込む度胸はない。
リパルサーマトリクス付きのベルトをしていれば、この高さでもフォローは可能だが。
「そう言えば……ミーティオたちは歩いてここまで来たの?」
「途中までは徒歩でしたね……結局姉さんが迷ったので、途中から交通機関ですg」
「余計なこと言うな」
クルネアの言葉に答えたシェプルの頬が、むにぃっとミーティオにつねられた。
「相変わらずだなオイ、そんな関係が良く続いてんなw」
「姉さんとの関係はお互いに自然体なのですよ、色々なことを含めて1つの絆なのです」
「姐さんは懐が広いんすよ、おいらもお供出来るならしたいっす」
スジーノが言う「姐さん」は、もちろんミーティオのことである。
その自由人そのものといった振舞いに、感化される者もいるということか。
「人気者ねぇミーティオはw」
「同族からはほとんど相手にされないんだけどね……」
苦笑いするミーティオに、クルネアが苦笑を返し、シェプルやスジーノに拡散する。
今度はギータも共感しているような表情だ。
そんな種族間交流が――銀河社会では日常風景なのである。
|
|
|
|
【Meking Memo/設定補記】
2024年に初めて執筆したエピソード。
「銀河社会の日常」を表現するためのショートストーリーの1つであるが、
実は漫画作品『世界の終わりに柴犬と』に影響を受けて作った経緯がある(笑)
本家は人類がほぼいない終末世界を旅する女子高生と柴犬の日常を描いたものだが、
動物語を理解する少女と博識な柴犬ハルのマニアックな日常会話が面白く、
虚無主義的な世界観であることを忘れるコント風味の作風で知られる。
こののんびりした多種族コミュニケーションは、GDW世界観の銀河社会に似るため、
同作をモチーフにしたドラマを書こうと思ったのがきっかけであった。
(もちろん銀河社会は終末世界ではないので、背景の前提条件は違っているのだが)
舞台として設定したオルガーナゲイト・テクトラクタのオルファーマ自治区も新設定で、
「銀河社会の日常風景」の裾野を拡げる狙いもある。 |



